Loquat








びわは古来より、様々な療法に用いられてきました。
特にびわの葉の利用法が広く知られており、現在でも民間療法などで広く活用されています。
花や果実、根や種子にも体に良い成分が含まれています。
また、びわの種子は「天神」とも呼ばれています。
この天神という言葉は今でも残っていて梅の種子などを「天神さま」と呼ぶのは
体に良いすぐれたびわの種子をそう呼んだことから起こったものとも言われています。



日本では約1300年前にはすでに
「びわ葉」を健康のために用いたとする資料があります。
当時はお寺で、病める人々のために僧侶が
「びわ葉」を使用した療法を施したそうです。
今でも、お寺の境内にびわの木が植えてあるのをよく見かけますが、
こうした理由によるものです。
江戸時代に入ると、びわの葉と一緒に薬草を煎じた
「枇杷葉湯」(びわようとう)が庶民に親しまれるようになります。
この「枇杷葉湯」は、夏の暑さをしのぎ、疲れた体をいたわる効果があるとして
、京都や江戸の夏の風物詩として庶民に親しまれました。
こうして、「葉を当てマッサージする」「飲料にして飲む」など、
各地でびわを用いた様々な民間療法が広まり今日に至ります。
「中薬大辞典」によると、「肺を清め、胃を和ませる。
肺熱による痰咳、胃熱による嘔吐を治す。」とも記載されています。
言い伝えでは、葉を洗って刻み、乾燥させ、お茶として飲む。
痰の少ない乾いた咳や、口の渇き、暑気にあたり弱った胃の回復によいとされ、
浮腫や利尿にも用いられたようです。
また黒くなった晩秋の頃の葉は、
リンパの腫れや筋肉痛などに直接貼るとよいとされ、
葉を煮出した液が湿疹やあせも、アトピーに良いとされています。
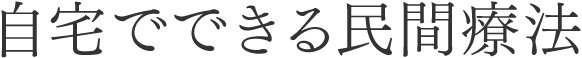
びわには有効成分が非常に多く含まれており、古くから健康を維持する方法として利用されてきました。
現在でもその効能を生かして様々な療法が用いられています。
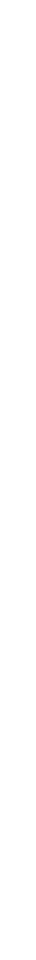

お釈迦様の経典のひとつ「大般涅槃経」(だいはつねはんきょう)の中で、
「大薬王樹、枝、葉、根、茎ともに大薬あり、病者葉は香をかぎ、手に触れ、
舌で舐めて、ことごとく諸苦を治す」と記されています。
また、びわの木を「大薬王樹」、びわの葉は「無憂扇」と呼ばれ、
大変優れた薬効があると伝えられています。
栽培については、「中国果樹分類学」(1979年・徳浚著)によると、
西暦1世紀に書かれた中国の「西京雑記」にびわの記述があり、
遅くとも後漢(25~220年)の時代には栽培されていたと記述されています。


また、中国の明の時代(1366~1644)に発行された「本草綱目」
(1956年、李時珍著)の中で、びわの葉の効能を次のように述べています。
「胃を和し、気を下し、熱を清し、暑毒を解し、脚気を療ず」つまり、
胃腸を整え、気を落ち着かせ、熱を下げ、暑気あたりのような状態をおさめ、
脚気を治すということです。その他、鼻血の止まらないときとか、
酒の飲みすぎで鼻が赤くなったもの、吐き気などにも用いることが
記載されています。漢方薬とは別に、江戸時代に日本で創作された
ビワの処方があり、これを枇巴葉湯といいます。
詳しく調べると中国の明時代の変法とう説もありますが、
漢方処方には枇巴葉湯はなく、「和漢三才図会」では寺島良安も和法であると
述べています。この処方は、びわの葉と甘草、桂皮、木香など7種の生薬で
構成されており(薬草の種類は出典の文献によって異なります)、
主に暑気あたりや、胃腸病に用いられていたようです。
禅文化研究所の文献によれば、びわの葉療法は鑑真和尚(唐招提寺建立)が中国から日本に伝えられたとされています。
特に、時の天皇である聖武天皇の后の光明皇后が730年に「施薬院」(今の病院)を創設し、
そこでびわの葉療法が行われていたとあります。
それ以来お寺の僧侶が寺の境内にびわの木を植えて檀家の人々や村人にびわの葉療法を行い、病人を救ってきました。
ところが、一般には「びわの木を庭に植えると病人が絶えない」とか
「縁起が悪いのでびわの木を庭に植えてはならない」という迷信がありました。
いったいナゼでしょうか・・・。
※その昔、薬など一般的でない時代に、病気になると病気が治るようにと神様や仏様に願い事をし、そのときに特別なものとして渡されたのが、びわの葉や種だったようです。その理由は、薬効成分があり、万病に効くのを知っていてのことでしょう。それで病気が治れば、評判になる。
一般の家庭でびわを植えられてしまうとありがたみがなくなるので、びわは縁起でもない樹木であるとしたのだろうということも言われています。
※びわは栄養が豊富だから、食べ過ぎると害が出る
びわの木がある家にびわに薬効があることを知った病人が、葉や種をもらいにたくさん押しかけた事実を、病気がやって来ると誤解して生まれたものと思われます。
※埼玉県八潮市には、枇杷の予兆として「枇杷が花を沢山付けると豊作」というのが伝承されています。しかし、おなじ八潮市内でも興味深いことに、屋敷に植えてはいけない理由として『枇杷の実が性器に似ていて種がとれて子供ができなくなる』『後継者ができない』とも伝承されています。
伝承の多くは病気に対する畏怖した事が多く聞かれています。
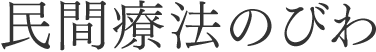
びわには有効成分が非常に多く含まれており、古くから健康を維持する方法として利用されてきました。
現在でもその効能を生かして様々な療法が用いられています。
古来からわが国に胃伝えられた療法は、おそらく生のびわの葉で体の痛いところをなでたり、患部に貼っておいたことと思われます。ビワの葉は色の濃い古い葉を使用します。これを患部にあてて貼っておくと、体温によりビワの葉が温められて薬効成分が少しずつ皮膚から浸透し、痛みや腫れがとれたりします。例えば、捻挫や末期がんの痛みに奏効したという事例があります。体温で葉がすぐパリパリになるので、葉の上にラップや油紙を貼っておくとより効果的だそうです。
臨済宗の寺、金地院(こんちいん:静岡県引佐郡細江町)で大正時代の中ごろから第2次世界大戦のころにかけて河野大圭(こうのたいけい)師が行った療法で、これにより難病に苦しむ20万人以上の人々が救われたといわれています。
びわの葉に棒もぐさを使用する温灸法で、一般に大変よく普及しています。栃木県真岡市の長蓮寺が発祥の地と言われています。
特殊な器具の先端部にびわエキスをしみこませ棒もぐさを使って行います。
遠赤外線の熱でびわエキスを蒸気化して皮膚から浸透させます。
びわの葉を煎じて飲む方法です。びわの葉に肉桂(にっけい)、霍香(かっこう)、莪述(がじゅつ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、木香(もっこう)、甘草(かんぞう)の7品目を同量混ぜ合わせて、煎じて作ったものです。 江戸時代、京都の町のあちこちに、夏の夕涼みの床机が見られるようになると、決まって「京都烏丸のビワ葉湯はいらんか-」と物売りの声が聞かれたそうです。昔から夏負けや暑気あたり、食中毒や大腸カタルの予防の保健薬として愛飲されていました。胃腸の弱い人、咳・痰きり、慢性気管支炎などによいとされ、尿の出が悪くむくみのある場合には利尿作用を発揮すると言われています。また、濃く煮出した煎じ汁は切り傷、虫刺され、アトピー性皮膚炎、かぶれ、やけど、日焼けによいとされます。
びわの葉を煮出し、煮出し湯をその葉と一緒に風呂に入れます。
利用価値が見直されつつあるびわの種は、枇杷核として薬用に用いられています。3~6グラムを水で煎じて用い、炒って食用にしてはならないとされています。薬効は、疏肝利気、化痰鎮咳で、咳を鎮め、水腫を治し、疝気を治すとされています。また瘰癧には、枇杷核を綱かく砕いて、酒に混ぜて張ると良いとされています。
びわの葉を使った化粧水も市販されています。
「名医別録」の中品に収載 [起源]バラ科のびわの葉 [薬理作用]抗炎症作用
[用途]鎮咳、去痰、利尿、健胃、鎮咳薬として久しい咳、暑気あたり、浮腫などに用いる。また、民間的に皮膚円やあせもに葉を煎じた汁で湿布する。
浴用剤としても用いられる。葉は、「枇杷葉」と称し肺に熱があるときの咳を止め、咽の渇きを除く効果があります。乾燥させた葉をお茶のように飲むとよいでしょう。
皮膚炎には煎じた汁で湿布します。

古くから調味料として用いられてきたお酢は、近年になって、私たちの体に“うれしい”働きをたくさん持っている事が、分かってきました。
一方で、びわは初夏の美味しい果物としてだけでなく、古来より人々の生活に根差した身近な薬木として重宝されてきました。
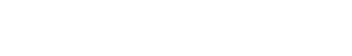
ビワミンは小さなお子様からお年寄りまで、
安心して美味しく飲めるお酢の芸術品ともいわれる逸品です。
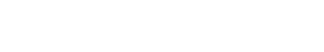
びわには古来より、枝・葉・根・茎・種すべてに
よい成分が含まれ、体を健康にするといわれています。

ビワミンは“美味しく飲めるお酢”として、
使用するお酢にこだわっています。


〒861-4133 熊本県熊本市南区島町2丁目5-16
TEL 096-358-3144 FAX 096-358-2187
営業時間 9:00~17:30(日・祝日は休み)
